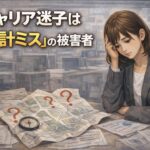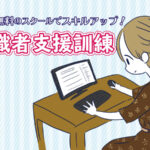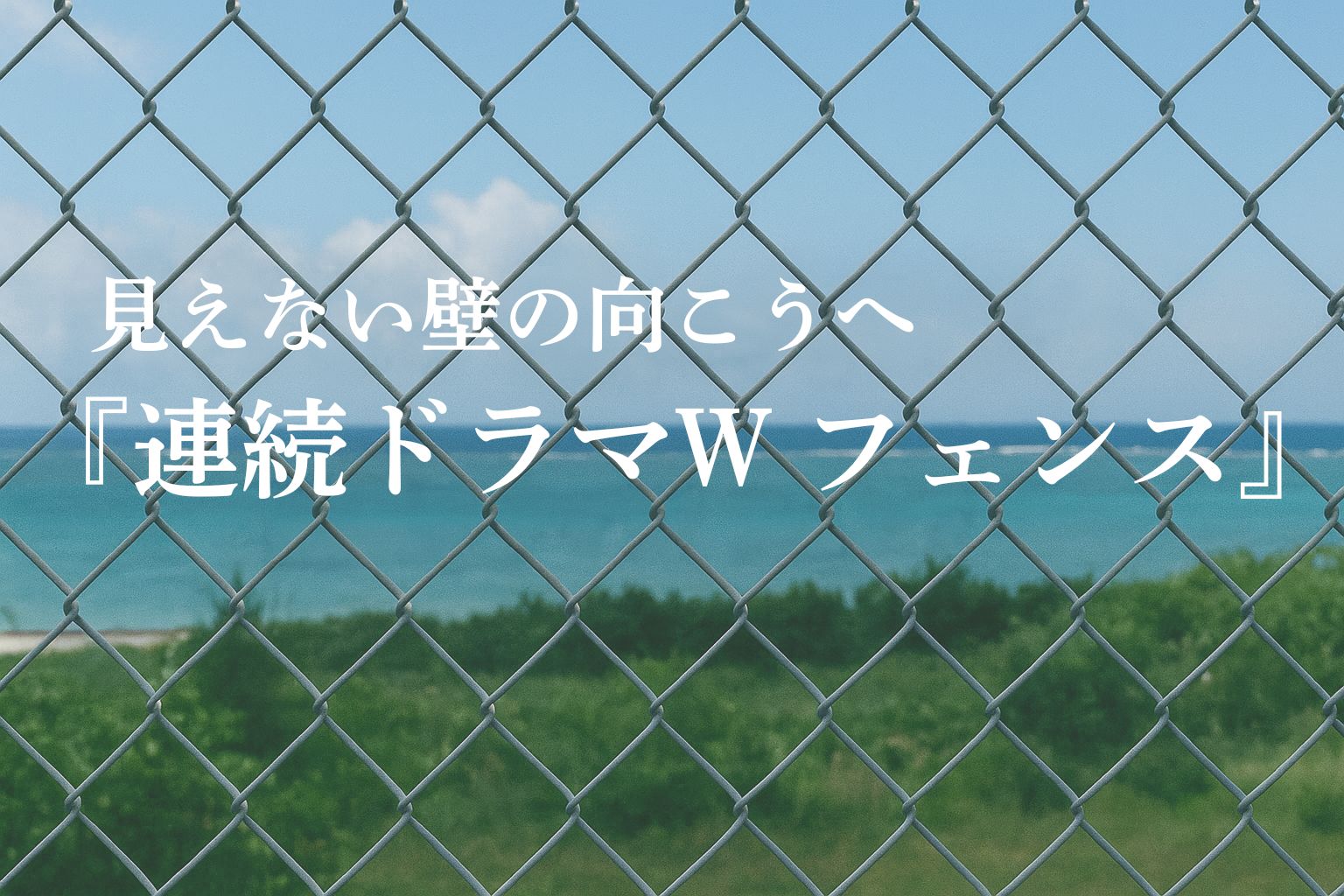
2023年にWOWOWで放送された『連続ドラマW フェンス』(脚本:野木亜紀子)は、沖縄を舞台に「報道」「性暴力」「基地問題」という、メディアが長く避けてきたテーマに切り込んだ社会派ドラマだ。
主人公は、東京で雑誌ライターとして働く小松綺絵(松岡茉優)。彼女は、上司の命令で米兵による性暴行事件を取材するため、沖縄へと飛ぶ。
被害者として名乗り出たのは、米軍人の父を持つ大嶺桜(宮本エリアナ)。カフェバー「MOAI」を営む彼女は、キーに事件の経緯を語りながらも、どこか違和感を残す。
取材を進めるうちに、キーは沖縄県警の伊佐(青木崇高)と再会し、米軍犯罪の捜査がいかに複雑で理不尽な構造の中にあるかを知る。
やがて桜が“誰かを守るために”証言を変えている可能性が浮かび上がり、キーは取材者として、ひとりの人間として、この地に刻まれた「見えないフェンス」と向き合うことになる。
この記事の目次
野木亜紀子が描く「構造としてのフェンス」
脚本を手がけた野木亜紀子は、社会に潜む構造的な“壁”をエンタメの文法で描く稀有な作家だ。
『逃げるは恥だが役に立つ』では「労働と契約」、『MIU404』では「正義と暴力」を描いたように、彼女の作品には一貫して「見えない仕組みへの違和感」がある。
TOKIONのインタビューで、野木はこう語っている。
「沖縄の問題を描きたいのではなく、“日本の問題”として描きたかった。誰の心の中にも“見えないフェンス”がある。」
この“フェンス”という比喩が、ドラマ全体を貫いている。
基地の周囲に立つ物理的なフェンスだけでなく、
「見ないふりをする社会」「声を上げにくい構造」「報道できない現実」。
それらすべてが、無数のフェンスとして私たちの目の前にある。
エンタメの形をした“痛みの物語”
『フェンス』が素晴らしいのは、社会派ドラマでありながら、登場人物の感情の機微が丁寧に描かれていることだ。
松岡茉優演じる小松キーは、決して完璧な記者ではない。東京の空気をまとい、最初は「取材対象」として沖縄を見ていた彼女が、次第に“他人事ではない現実”へと引きずり込まれていく。
一方、宮本エリアナが演じる桜の存在は、この物語の“痛み”そのもの。
彼女の複雑な出自、沈黙、そして「守りたい誰か」が象徴するものは、国家と個人、加害と被害、語ることと黙ること――そのすべての狭間で揺れる日本社会の縮図のようだ。
沖縄の“語れなさ”に寄り添うまなざし
本作を観ていて、心を掴まれたのは「沖縄の人々の複雑な感情を単純化せずに描いている」という点だ。
上間陽子さん(社会学者・『裸足で逃げる』著者)は、Hanakoでのレビューの中でこう述べている。
「キーは沖縄の理不尽な現状をしっかり怒ってくれます。しかし沖縄の人たちは現実でも自分の苦しみをあまり言葉にしません。
基地があるから危ないと思う人もいれば、その基地で働いている人もいる。
この島でいろんな他者と共に生きていくためには、軍用機が飛んでいても知らんぷりをしなくてはいけない。
そんな沖縄の人々の単純化できない心の内までも丁寧に描かれていたので驚きました。」
—— 上間陽子『Hanako』(https://hanako.tokyo/learn/372085/)
上間さんの言葉どおり、『フェンス』の登場人物たちは誰も“正義の側”に立っていない。
誰もが何かを守るために黙り、折り合いをつけながら生きている。
その沈黙の中にある痛みを、ドラマは真正面からすくい取ろうとしている。
暴力と回復――当事者の物語を誠実に描く
物語の中心にあるのは、米兵による性的暴行事件。
これは「過去の事件」ではなく、今も続く沖縄の現実だ。
上間さんは同じレビューの中で、次のようにも語っている。
「私は職業柄、性的虐待や性暴力を受けた女性たちが身近にいます。だからこそ、この手の作品は当事者を傷つけるような演出がないかヒヤヒヤしてしまうこともある。
しかし本作は女性たちを社会の片隅へ追いやってきた構造の問題までしっかり描いてくれていて、そこに誠実さを感じました。
トラウマと共に生きるサバイバーがどうやって前を向いていくのか、その“回復の回路”までも描こうとしてくれていたのには救われる思いがしました。」
—— 上間陽子『Hanako』(同上)
この視点がまさに、『フェンス』の真価だと思う。
“暴力”を単なる事件として消費せず、そこから“生きること”を描こうとする誠実さ。
それは報道でも政治でもなく、「人間の尊厳」という根源的なテーマだ。
見えない“利害の網”の中で生きるということ
上間陽子さんが指摘する「沖縄の複雑な沈黙」は、
決して沖縄だけの問題ではないと感じた。
私は東京近郊に住んでいて、横須賀の基地周辺に知り合いが多い。
「自分の家族はBASEで働いてるよ」という声もよく聞く。
基地で働き、そこで得た収入で生活している人たちがいる。
その現実を知ると、単純に「基地反対」とは言いきれない複雑さもわかる。
その地を侵略するのに恩恵も与えて、ステークホルダー(利害関係者)にしてしまう。
そして、口を封じてしまう。
それは沖縄だけではなく、どこの土地にも起こりうる構造なのだと思う。
“支配と依存”“暴力と生活”――相反するものが日常の中で共存している。
そうした現実を見つめるまなざしこそ、『フェンス』が提示する問いなのかもしれない。
基地というフェンスの向こうにあるのは、遠い沖縄ではなく、私たち自身の問題だ。
生存戦略としての「想像する力」
『フェンス』は、怒りや悲しみだけを残す作品ではない。
むしろ、そこに生きる人々の「想像する力」を描いている。
他者の痛みに想像力を向けること、それ自体が現代を生き抜くための戦略なのかもしれない。
“フェンス”は越えるものではなく、見つめるもの。
見ようとする意志が、現実を変える最初の一歩になる。
『連続ドラマW フェンス』を今すぐ観る
沖縄を舞台に「見えないフェンス」と向き合う社会派ドラマ。
気になった“今”が観どきです。
※本リンクはアフィリエイトを利用しています。リンク経由のご購入・ご視聴は当サイトの運営支援になります。ありがとうございます。