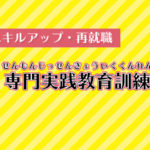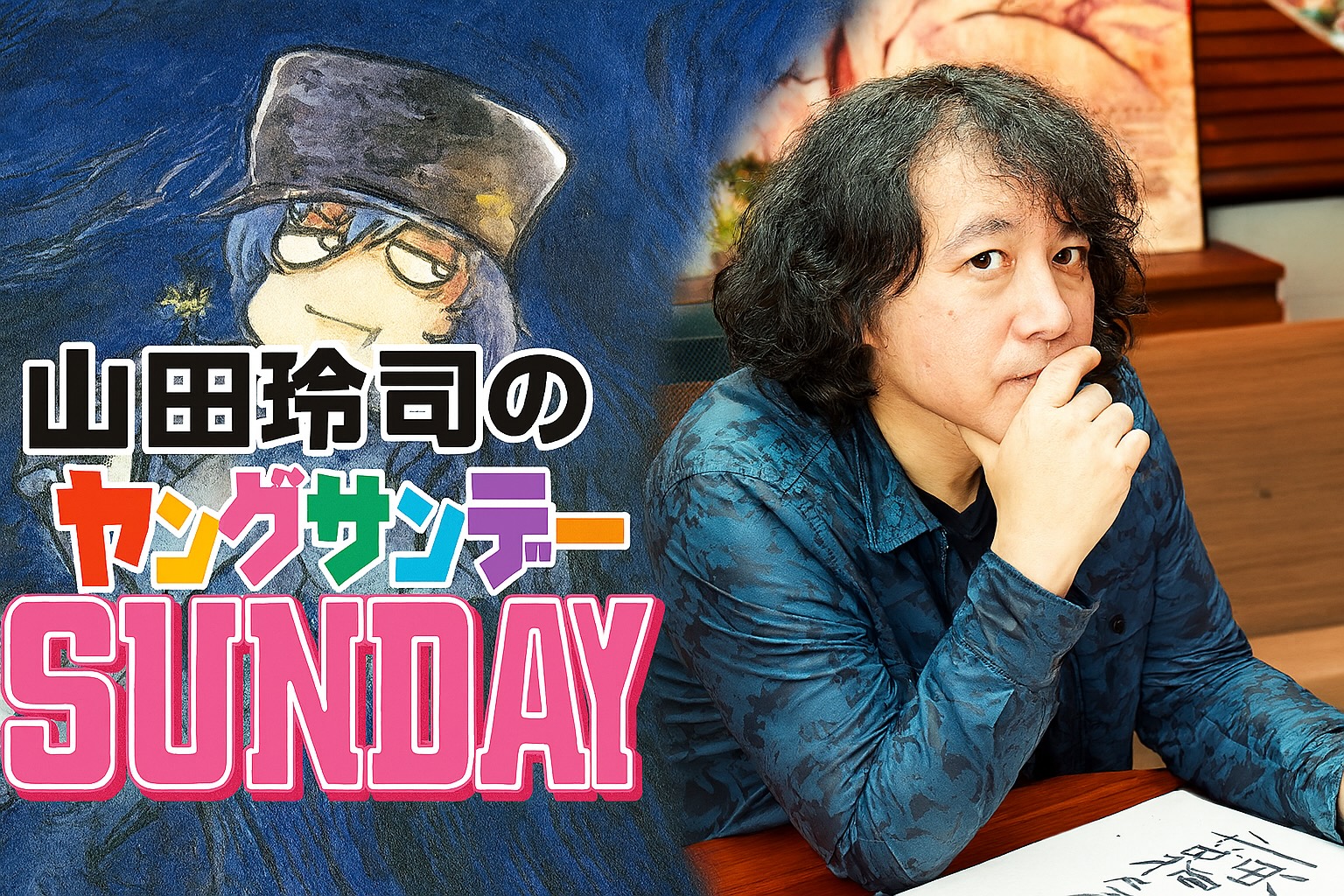
今日は私がひそかにリスペクトしている大人、漫画家・山田玲司さんについて書きます。
漫画家でありながらYouTubeチャンネル「山田玲司のヤングサンデー」などを通して、社会、カルチャー、哲学まで語りまくる、唯一無二の存在。
ただ“知っている”だけじゃない。体験や実感をもとに言葉を届けてくれるから、心にスッと入ってくる。
なんというか、「知性と情熱と人間くささ」が同居している人。
私にとって、「こういう大人になりたいな」と思わせてくれる稀有な存在です。
この記事の目次
🎙️ 1. 教養をエンタメに変える人
まず何がすごいって、教養が深すぎるのにめちゃくちゃ面白い。
文学、歴史、心理学、漫画、アニメ、東洋思想まで…あらゆるジャンルを横断して、解説してくれる。
▶️おすすめ動画:
これらのアニメって、視聴後に「なんとなくわかったような気がするけど…」ってモヤモヤが残る作品。
でも山田さんの解説を聞くと、
「うわ、それがテーマだったのか!」
「このセリフ、そんな意味があったんだ…!」
と、“気づき”がめちゃくちゃある。まるでアートの“目利き”みたいな感覚。
🌿 2. 東洋思想のまなざしを感じる
山田さんの話には、仏教や老荘思想などの「東洋の知恵」がふっと現れるときがある。
たとえば「執着を手放す」「自然体で生きる」といった考え方に、私はすごく救われました。
▶️おすすめ動画:
これはもう半分、東洋哲学の授業。
でも小難しくなくて、**「人ってさ、こういう時つらいよね」**というリアルさがあるから、ちゃんと届く。
💥 3. 原作者としての声をあげてくれる
最近の配信では、原作漫画家がアニメ化される際に置かれる理不尽な立場についても語っていました。
「作家が搾取されるこの業界、おかしいよね」
と真正面から言ってくれる姿に、私はすごく安心した。
逃げない人。 そして同業者として、ちゃんと痛みを共有してくれる人。それって、ほんとに勇気のいることだと思う。
🎮 4. オタクカルチャーを知性で語る
YouTube「ヤングサンデー」では、漫画・ゲーム・アニメといったカルチャーを語り倒す企画が豊富。
しかもただの感想じゃなくて、歴史や社会背景まで引きずり出してくれるから、聞いてるこっちが賢くなる。
「知るって、楽しいことなんだな」
って素直に思える。
知識と好奇心をつなぐ“翻訳者”としてのかっこよさが、山田さんにはあります。
👤 5. 「大人」の理想像をくれる存在
-
弱さを語る
-
若者の味方でいる
-
お金や社会に違和感があるときは、ちゃんと声を上げる
-
自分の生き方を誇りにしている
そういう姿勢が、どれも**「強く見せる」のではなく、「真摯であること」に貫かれていて、本当にかっこいい。
私はこんなふうに、“自由に、誠実に、大人を生きている人”**に憧れるのです。
💣 6. 『オッペンハイマー』解説に見る、戦争と人間の本質
そして最新の配信では、映画『オッペンハイマー』を取り上げていました。
原爆を開発した科学者を描いたこの重たい作品を、歴史・宗教・人間心理を横断して読み解いていくスタイルが圧巻です。
▶️【映画オッペンハイマー解説】山田玲司が語る「科学と人間の限界」
この回では、単に「映画の内容を解説する」だけではなく、
-
科学が暴走する理由
-
ナチスドイツとアメリカの政治的背景
-
仏教的視点で見る“因果”と“業”
など、あらゆる視点からオッペンハイマーという人物とその選択を読み解いていました。
特に印象的だったのは、
「科学や知識には“歯止め”が必要なんだ。それを支えるのが“人間としての倫理観”なんだよね」
という言葉。
映画では語られなかった部分まで含めて、**「歴史と人間の深層を理解するヒント」**が詰まった回。
重たいテーマに対して真正面から向き合い、逃げずに語ってくれる姿勢が、やっぱりかっこいい。
🪶補足:観た人に“もう一度観たくなる”視点をくれる人
山田さんの解説を聞いていると、作品の見え方が変わる。
「あの場面、そんな意味があったの⁉︎」と目から鱗が落ちる瞬間がある。
ただのおしゃべりじゃなくて、
“作品に宿った魂を読み解く”解説者なんだなと実感します。
📚 7. 萩尾望都の革新を語る、“少女マンガ”を超えた思想の話
少女マンガの巨匠・萩尾望都さんの解説回も、まさに「山田玲司にしかできない語り口」でした。
萩尾望都さんの作品大好きなんです。。
この回で語られるのは、単なる作品紹介ではなく、
-
少女マンガという表現の枠を壊した先駆者としての萩尾望都
-
ジェンダーとセクシュアリティの探求者としての姿勢
-
そして、人間の根源的な孤独や喪失を描く哲学者としての一面
「SFもBLもやってた。でも、萩尾望都が描いていたのは“人間の救い”だったんだよ」
山田さんのこの言葉がすべてを物語っているように感じました。
また、「ポーの一族」「トーマの心臓」「11人いる!」といった名作を、
時代背景や萩尾さんの内面世界と絡めて読み解くことで、
作品の深みがぐっと増して見えてくる。
💫 少女マンガを“思想”として読み解く姿勢がすごい
この回を観て思ったのは、山田玲司さんは
少女マンガ=「軽くて甘い読み物」なんて思っていないということ。
むしろ、
「少女マンガのほうが、人生の真実を描いてる時がある」
というまなざしで、作品を“思想”として捉えている。
創作する人間の「内なる痛み」や「魂の叫び」に、まっすぐ向き合ってくれる。
だから山田さんの語る“解説”は、どこか鎮魂のようでもあり、祈りのようでもあるんです。
🪞 結局、何を語っても「人間を語っている」人
アニメでも映画でもマンガでも、どんなジャンルでも、
山田さんの根っこにあるのは**「人間ってなんだろう?」**という探究心。
-
科学の闇を語ればオッペンハイマーになる
-
少女の痛みを語ればウテナや萩尾望都になる
-
家族や愛を語れば輪るピングドラムになる
どこにいても、人間の内側に光を当てようとする姿勢が一貫しているんですよね。
✨ まとめ:大人になるって悪くないかも
山田玲司さんの動画を観ると、
「大人になるって、つらいことだけじゃない」
「自分の人生を好きにしていいんだな」
と思えてくる。
すでに知っている作品でも、彼の視点で観直すと全然違って見える。
生き方に迷っている人、何かを創りたいと思っている人、ぜひ一度、観てみてください。
🎧おすすめ動画まとめ: