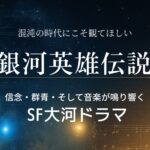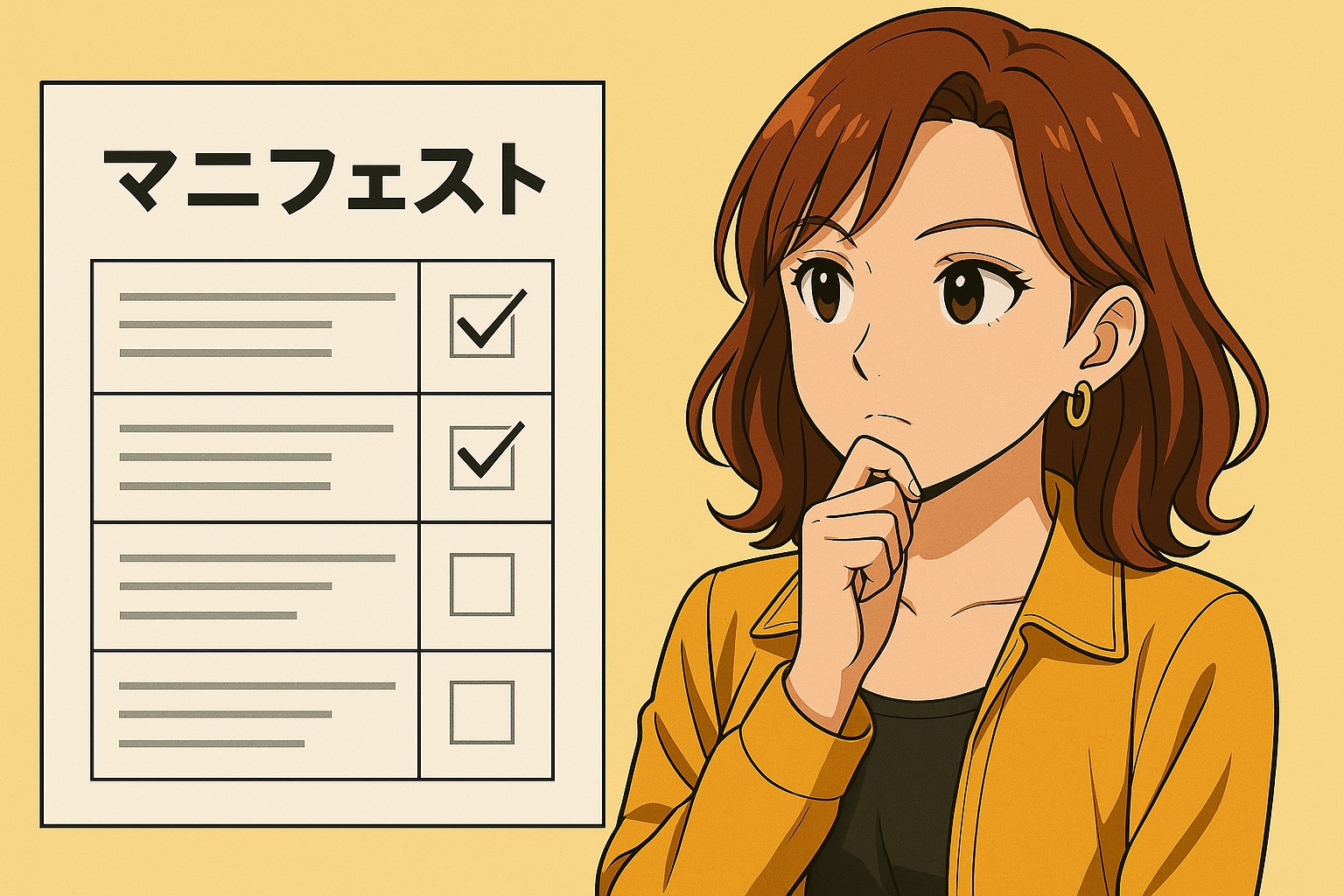
こんにちは、なつめです。
今日は、X(旧Twitter)で見かけた投稿をきっかけに、どうしても書きたくなったことがあります。
それは「選挙に行く意味」についてです。
この記事の目次
🕊 黒柳徹子さんの言葉が胸に刺さる
「どんなにあなたがいい勉強をしていても
いい恋愛をしていても
何をしても
そんなものはいっぺんにしてなくなっちゃうのが戦争なので
絶対に戦争はしてはいけないということを
みなさんに知っていただきたい」
— 黒柳徹子さん
この言葉に、私は立ち止まりました。
どんなに日々を大切に生きていても、
積み重ねてきた努力も、未来への希望も、
一瞬で壊れてしまうのが「戦争」だという現実。
この静かな、けれど強いメッセージを聞いて、
「だからこそ選ばなきゃいけない」と感じたんです。
🎤 無礼に対しても言葉で返すという強さ
もうひとつ、選挙演説中に起こった出来事も目にしました。
神奈川選挙区の候補者、大椿ゆうこさん(社民党)が、
ある男性から侮辱的な態度をとられた場面。
けれど彼女は怯まず、
その男性と言葉で向き合い、意見を受け止め、丁寧に対話をしていたんです。
これは、すごく勇気のいること。
怒りや悔しさをぐっと飲み込んで、
「言論で闘う」「対話で進める」って、
とても誠実で、理想的な政治家の姿だなと感じました。
🗳 今回の選挙は「参議院選挙」。任期は6年!
今回の選挙は、参議院選挙です。
当選した議員の任期は、なんと6年。
小学生が入学して卒業するほどの長さです。
6年という時間の中で、
社会は大きく変わっていきます。
景気、税金、社会保障、教育、そして憲法。
そのすべてに関わるのが、「誰を国会に送るか」という私たちの選択。
「1票じゃ変わらない」と思っても、
その1票の積み重ねでしか、社会は動かない。
📘 憲法って「国民を縛るルール」じゃない
私が最近読んで、すごくわかりやすかった本があります。
📖 『檻の中のライオン』(楾 大樹 著)
この本では、
-
憲法を「檻」
-
権力を「ライオン」
にたとえて、
**「憲法は権力をしばるためのもの」**という考え方を解説してくれます。
わたしたち国民の自由や権利を守るために、
政治家が“暴走”しないように見張る仕組み。
それが「憲法」であり、「立憲主義」です。
だから私は、
改憲ではなく、憲法を守る立場の政党に投票したいと思っています。
🚫 差別を土台にした政治には、NOを
私は、差別や分断で成り立つ政治を、決して選びたくない。
たとえば、特定の人々――
外国人、LGBTQ+、貧困層、ひとり親、女性――
そうした人たちを「敵」として扱い、
「国をよくするにはあの人たちを排除しよう」と呼びかける政治。
そういう考えは、いじめと同じ構造だと思います。
そして、いじめのターゲットはいつだってころころ変わる。
いつか、自分がその矛先になるかもしれない。
だから私は、
-
意見の違いはあってもいい
-
あなたの意見も、私の意見も存在していい
-
一人ひとりの人間を、尊重し合える社会であってほしい
そう思っています。
意見を伝え合うことに、わたしたちはまだ慣れていないかもしれない。
でも、少しずつでも練習していこう。
怒鳴ったり、排除するんじゃなくて、言葉で伝えること。
それを大切にしたいです。
🗳 私が投票したいと思う政党・候補者
今回、私は神奈川選挙区で投票します。
比例代表も含めて、次のような考えの政党に心を寄せています。
-
社民党:立憲主義と平和主義を守る、現場に根ざした声を国政へ。
-
日本共産党:反戦・反差別・反原発など、市民の安全と自由を守る。
-
れいわ新選組:生活者の目線で、弱い立場の人を置き去りにしない政治。
どの政党も完璧ではないかもしれない。
でも、「どこに投票するか」じゃなく、
**「何を守りたいのか」で選ぶ」**という姿勢を大切にしたいんです。
💡 投票は、静かな革命。
-
言葉で闘う人を応援したい
-
暴力や無関心ではなく、対話ができる政治を
-
当たり前の暮らしと、小さな幸せを守りたい
-
誰もが“尊重される存在”として扱われる社会であってほしい
そんな願いをこめて、私は選挙に行きます。
あなたも、どうか忘れずに。
未来を変える一票を、ちゃんと使ってあげてくださいね。
🧾 今こそ、政治に“成績表”をつけよう
今回の選挙は、ただの人気投票じゃありません。
これは「これまでの政治がどうだったか」に対する、わたしたち一人ひとりの成績表です。
-
暮らしは豊かになりましたか?
-
物価はどうですか?
-
医療や子育て、介護の制度は使いやすいですか?
-
ジェンダー平等は進みましたか?
-
教育や将来への不安は減りましたか?
この数年間、自民党と公明党による連立政権は、わたしたちの暮らしにどんな影響を与えたでしょうか。
感覚的ではなく、自分の生活と照らして考えてみてほしいです。
🚫 私は「参政党」には投票しません
私は、女性差別や外国人差別を助長するような発言や姿勢を見せている政党には、絶対に票を入れません。
たとえそれが「正義」や「日本のため」と言っていたとしても、その中身に差別や排除が含まれていたら、それはもう「正義」ではないと私は思います。
たとえば参政党。
-
代表・副代表がマルチ商法のアムウェイと関わっていたこと
-
組織票を取り込む戦略的な活動
-
科学的根拠に乏しい陰謀論的な発信や、極端な排他思想
こういった動きには、強く警戒しています。
どれだけ「キラキラした言葉」で希望を語っていても、
差別を土台にした社会は、必ず誰かを傷つける社会になる。
その刃は、いずれ自分自身にも向けられる。
参政党は演説でデマもすごい
まとめている方もいらっしゃいます。
アムウェイぽさがすごい。
🧾 今こそ、政治に“成績表”をつけよう
今回の選挙は、ただの人気投票じゃありません。
これは「これまでの政治がどうだったか」に対する、わたしたち一人ひとりの成績表です。
-
暮らしは豊かになりましたか?
-
物価はどうですか?
-
医療や子育て、介護の制度は使いやすいですか?
-
ジェンダー平等は進みましたか?
-
教育や将来への不安は減りましたか?
この数年間、自民党と公明党による連立政権は、わたしたちの暮らしにどんな影響を与えたでしょうか。
感覚的ではなく、自分の生活と照らして考えてみてほしいです。
📻 武田砂鉄さんの「公約の振り返り」提案
TBSラジオ『武田砂鉄のプレ金ナイト』で、武田さんが選挙前におすすめしていたこと。
「前回の選挙で、各政党が掲げた公約を見返してみる。
それが実現されたかどうかを確認する。」
これ、すごく大事な視点だと思います。
選挙のたびに聞こえてくる“いいことばかり”の公約。
でも、本当にそれを実行したの?
という振り返り作業を、私たちは意外とやっていない。
武田さんが言っていたように、
こうした公約チェックや検証は、本来テレビ・新聞・ラジオといったメディアが徹底的にやるべき仕事なんですよね。
でも実際には、きちんと比較・検証している報道はまだ少ない印象です。
💡「言いっぱなし」を許さない、賢い有権者に
公約なんて、どうせ“言いっぱなし”でしょ?
と思ってしまうと、政治はますますいい加減になる。
だからこそ、国民が「覚えてるよ」「チェックしてるよ」と示すことが大事。
各政党に「選挙前の言葉に責任を持たせる」文化を育てていかないと、
政治家はいつまでも「ウケることだけ」言って終わりになってしまいます。
わたしたちは、選挙で政治家を選ぶだけでなく、
日々の関心とチェックで“育てる”立場でもある。
選挙前には、公約の振り返りを習慣にする。
そして、できていないことには「NO」、誠実に取り組んでいる人には「YES」と伝える。
そんな一票が、きっと政治を少しずつ変えていく力になるはずです。
📊 公約チェック! メディア&取り組み紹介
選挙前に「各政党が本当にやってきたのか?」を確認する機会を持つことが、有権者が政治家を育てる第一歩になります。いくつか、参考になる取り組みやメディアをご紹介します。
1. 経済同友会による「主要政策の比較・評価」
-
公益社団法人 経済同友会が、2025年7月に参院選前として、自民・公明・立憲・維新・国民・共産・れいわの7党について、
-
「中長期ビジョンと短期施策の整合性」
-
「政策の実現可能性(財源など)」
-
「構造改革への踏み込み度」
を評価し、比較レポートを公開しています 経済同友会、参議院選挙2025を前に各政党の政策比較・評価を実施
このレポートは、ただ並べるだけでなく、「将来に向けた道筋があるか?」「どうやって資金を集めるのか?」など、中身を厳しく見なす視点がとても有益です。 -
2. 「JAPAN CHOICE」—争点別に公約を一覧で比較
-
Webサービス『JAPAN CHOICE』では、経済・子育て・医療・外交・人権などの領域ごとに政党公約を表形式で比較できます Japan Choice。
自分にとって重要なテーマがあるとき、各党のスタンスがひと目でわかるのが魅力。実践的に使えるツールです。
3. 早稲田大学「#くらべてえらぶ」
-
早稲田大学デモクラシー創造研究所(旧マニフェスト研究所)が、参院選に際して「#くらべてえらぶ」というウェブサイトを公開 早稲田大学デモクラシー創造研究所+1Maniken〜地域経営のためのあたらしいマニフェスト研究所〜。
政党ごとに、政策テーマ別・一覧表形式でマニフェストを比較でき、**同研究所による“できばえチェック”**も掲載:
-
ビジョン提示があるか
-
財源や制度設計の具体性
-
“苦い薬”も含む信頼できる中身か、などを5項目で採点。
その結果、「ほとんどの政党にビジョンがない」「苦い政策を含んでいる姿勢が信頼できる本気度」などが分析されています。
4. 専門メディアによる争点別マニフェスト比較
-
環境や原発に詳しいメディアでは、各党のエネルギー政策を比較する記事も公開中 経済系メディアでは、「税制・物価・社会保障・防衛」など主要争点を整理し、与野党の立場差をわかりやすくまとめています 全専門家。
📝 どう活用する?有効活用のヒント
これらの比較サイトやレポートは、
-
自分の生活にかかわる“争点”を軸にして見る
-
「言いっぱなしの公約」にNOをつきつける前に、自分で確認する
-
メディア任せにせず、自分で“成績表”を持つ
という観点で活用すると、投票の質がぐんと高まります。
✅ まとめ:投票前の“振り返り習慣”を日常化しよう
-
メディアやシンクタンクによる比較・評価に目をとめる
-
自分が重視したいテーマで政党を比較する
-
「これをやるって言っていたよね?」を選挙前に再確認する
こうした振り返り作業が習慣になれば、政治家や政党は「言いっぱなしでは済まない」と感じるようになります。
それが、言葉に責任を持つ政治文化を育てる大きな一歩になるはずです。
🗳 最後に:選ぶ力は、あなたにある
誰に投票するかは、自由です。
でも「誰に投票しないか」もまた、大切な判断です。
私はこう思っています。
-
人を尊重できる人を、国会に送りたい
-
違いを認め合い、意見を伝え合える社会でありたい
-
声を上げた人が孤立しない世の中にしたい
-
暮らしを支える政治、命と権利を守る政治に戻したい
だから、私は投票に行きます。
その1票に、思いをこめて。